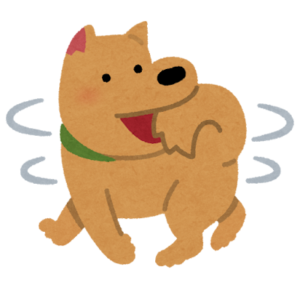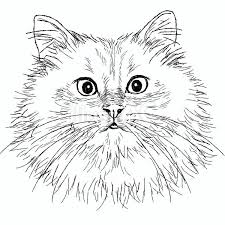行動の話
犬の尾追い行動は、行動学的問題と神経疾患の両方を並行して考えなければならない。抗うつ薬だけでなく、鎮痛薬も有効なことがある。
安定させるまではひと苦労なのに、その安定した状態はちょっとしたことで一瞬にして崩れ去ってしまう。神経に作用する薬剤には、すぐにはやめられないものがある。それは、突然やめると急激に悪化するからだ。抗てんかん薬や抗うつ薬の中 […]
認知症の犬が感じる不安感。それを見て飼い主が感じる不安感。悪循環を断ち切るために、犬の薬物療法とともに飼い主の心のケアも欠かせない。
夜中にずっと息切れをしていたという犬。呼吸器系の症状は深刻な事態を連想させる。しばらく前からなんだか様子はおかしかった。ストレスに弱くなっているような気がしていた。聴診で肺や心臓に異常音はないし、レントゲンでも胸の中に問 […]
布団やマットに排尿する猫。不適切な排泄の対策の一つとしてトイレの配置を工夫する。
猫の不適切な排尿。布団やマットなどの軟らかい素材に排尿することが多い。膀胱炎はない前提としよう。毎回十分量の排尿があって頻尿はない。2頭の猫に対してトイレは3つ。十分な数だ。だが、トイレ同士の距離が隣り合っている。 同居 […]
犬のハエ咬み行動の原因を探る。6つのカテゴリーのうちどれが該当するのか。飼い主は犬の行動をよく観察して獣医師へ伝えよう。
犬が天井を見上げて頭を左右に振り、何かを目で追いかける。時折パクッと口を動かす。犬には何かが見えていて、それを口で捕まえようとしているのか。それとも、見えている見えていないにかかわらず、そのような行動をするのか。傍で見て […]
怒る猫への対処法。背景にあるストレスを抑えてあえて距離をとる。
猫が飼い主に対して威嚇する。元々デリケートな性格であることが多いが、落ち着けるはずの自宅で家族に対して行動が変わることがある。こういうときは必ずきっかけがある。思い当たることもあれば、飼い主が気づいていないこともある。 […]
犬の尾追い行動は完治はしないが適切な薬と管理でコントロールできる。生涯にわたる飼い主の関わりが不可欠だ。
犬の尾追い行動は幼齢期から見られることが多い。自分の尾を気にする仕草、そしてクルッと回る。不快や葛藤を感じたときにもその行動をすることがあり、次第に悪化するケースもある。MRIまで含めた検査ではっきりとした原因がつかめな […]
吠える犬。エネルギー発散不足を解消し、不安や恐怖の感情を軽減する。
スケジュールを立てる能力を持っている動物は人間だけなのだそうだ。誰と会う、何をする。未来を計画して期日を決める。これが人間と他の動物を分ける特徴の一つらしい。他の動物は先を見越した行動はとらないとされている。ただし、「予 […]
犬の尾追い行動。早めに気づいて飼い主の関わり方を適切に変えることが将来の問題行動を防ぐことに役立つ。
飼い主からのちょっとした相談という形で尾追い行動の質問を受けることがある。ぐるぐるとしっぽを追いかける行動。尾追い行動は柴犬で見かけることが多いが、それ以外の犬種でもときどき見かける。 尾追い行動の原因を絞り込むためには […]
常同行動は不安や葛藤、高揚といった感情がきっかけになる。薬物と行動療法で神経回路の再構築と行動修正を目指す。
手術後に患部をしきりに気にするようになる犬は、元々デリケートなことが多い。窓の外に見える鳥、インターホンの音、来客。様々な刺激がスイッチとなって吠える。吠えることで嫌なことを排除できた成功体験が拍車をかけるのかもしれない […]
前に進みたいけど進めない。散歩中の犬の葛藤。犬とすれ違うときにどう対処すればよいか。
犬の散歩中、遠くから同じように犬の散歩をしている人がこちらに向かってくる。このままだと至近距離ですれ違うはずだ。こっちの犬の耳が前に向く。前方に注目しているのがわかる。目の色が変わった。あっちの犬にロックオンだ。 前のめ […]