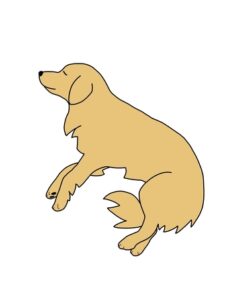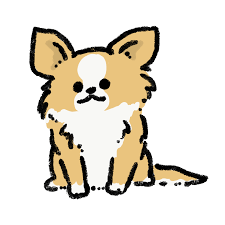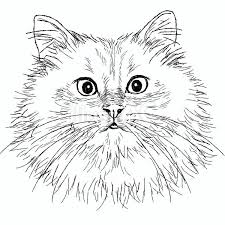季節性アレルギーの発症期間は、延長している。5月から10月まで、湿気、花粉、飛散粒子に要注意だ。
新緑の季節である5月から、カモガヤやオオアワガエリといったイネ科植物が河川敷や道端に繁茂してくる。モリモリと丈を伸ばしてたくましい。夏の花粉症の原因だ。目の周りや腕や脛の毛が薄くなった犬の来院が増えた。 そのうち6月の入 […]
けいれんを止めるだけでも意味はある。原因がそのままでも許されるケースとは。
けいれんを起こしたとの一報が入った。老犬が飼い主に抱きかかえられてやって来た。診察台に横たえられた犬は、意識はおぼろげで少しもがくように前足を動かしている。自宅から病院に到着するまでの間に激しいけいれんは治まっていたよう […]
布団やマットに排尿する猫。不適切な排泄の対策の一つとしてトイレの配置を工夫する。
猫の不適切な排尿。布団やマットなどの軟らかい素材に排尿することが多い。膀胱炎はない前提としよう。毎回十分量の排尿があって頻尿はない。2頭の猫に対してトイレは3つ。十分な数だ。だが、トイレ同士の距離が隣り合っている。 同居 […]
基準値内でも下がってきたら、要注意!知っておくべき抗てんかん薬の耐性発現。
安定していたのに1年ぶりにけいれん発作を起こすということはある。すぐにいつも飲んでいる薬に加えて別の薬を追加する。けいれんを抑える作用が早く現れる、頓服で使える薬だ。特発性てんかんと確定診断はついている。 発作型の変化は […]
犬のハエ咬み行動の原因を探る。6つのカテゴリーのうちどれが該当するのか。飼い主は犬の行動をよく観察して獣医師へ伝えよう。
犬が天井を見上げて頭を左右に振り、何かを目で追いかける。時折パクッと口を動かす。犬には何かが見えていて、それを口で捕まえようとしているのか。それとも、見えている見えていないにかかわらず、そのような行動をするのか。傍で見て […]
腫瘍の脳転移を疑った犬に何ができるか。そうなる前とそうなってしまったときにできること。
気づいたときには完治が難しいだろうと思われる状態になっていることはときどきある。例えば甲状腺がんを抱えた犬。喉元に硬い塊。大きすぎて経験上これは厳しいと感じる。治療のために検査に進むのか緩和ケアだけにするのか飼い主と相談 […]
折れ耳のスコティッシュフォールドと、反り耳のアメリカンカール。辛いのは、関節の障害か、耳の汚れか。
野生の動物の世界に、垂れ耳や折れ耳は存在しない。本来の形質は、立ち耳である。しかし、身近な犬や猫、その他の家畜では、垂れ耳や折れ耳をよく見かける。これは、品種改良で人為的に作り出したり、人間に従順な個体を選抜して、世代を […]
怒る猫への対処法。背景にあるストレスを抑えてあえて距離をとる。
猫が飼い主に対して威嚇する。元々デリケートな性格であることが多いが、落ち着けるはずの自宅で家族に対して行動が変わることがある。こういうときは必ずきっかけがある。思い当たることもあれば、飼い主が気づいていないこともある。 […]
1剤でコントロールができないてんかんは、2剤、3剤と微調整を重ねて安定させる。
てんかんの投薬治療にはスタンダードがある。初めから2剤や3剤を使うといったことをすると副作用が強く出る。突っ立たままボーっとする。触ればその刺激で目は開くが手を離すとユラ~っとして目を閉じてしまう。薬が効いている証拠では […]
犬の尾追い行動は完治はしないが適切な薬と管理でコントロールできる。生涯にわたる飼い主の関わりが不可欠だ。
犬の尾追い行動は幼齢期から見られることが多い。自分の尾を気にする仕草、そしてクルッと回る。不快や葛藤を感じたときにもその行動をすることがあり、次第に悪化するケースもある。MRIまで含めた検査ではっきりとした原因がつかめな […]