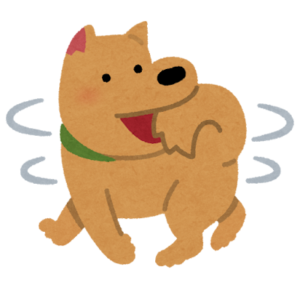物音に対して敏感過ぎる猫。それが異常行動に伸展する場合には聴原性反射性発作を疑う。
キビキビして見るからに活動的な猫はその視覚や聴覚も鋭いことがあり、例えば、ビニールのガサガサ音や家族の人の素早い動きなどに驚く。このように、引き金は視覚刺激と聴覚刺激だ。刺激に対してピキーンと一瞬にして神経が高ぶる。瞳孔 […]
野性の血が濃いベンガル。それゆえに問題行動が現れやすい。矯正はできないので、ともに暮らすときはすべてを受け止めよう。
当院の行動診療では、野生の猫種に近縁な猫は、品種の特性上、期待する効果を得られないかもしれないので、その点を了承いただいた上で受診を検討していただいている。「野生の猫種に近縁」とは、野生猫とイエネコの混血種のことだ。例え […]
ガクガクガクッ。電撃的な体のビクつきは、ミオクロニー発作を疑え!
腰を抜かす、プルプル震える、グルグル回ってバランスを崩してへたり込む。これだけでは原因が何かはなんとも言えないが、これが、ガクガクガクっと体が小刻みに上下に揺れて尻もちをつく、という表現になれば、ピンと来る。さらに、光を […]
排尿でも排便でも、トイレの失敗は生きにくさの表れなのかもしれない。猫の暮らしぶりから心模様を察してあげよう。
猫がどの程度ストレスを感じているかは、飼い主にはわからないことが多い。いつもと変わらないけど…、そんな風には見えないけど…。診察室で飼い主からこのような言葉をよく聞く。しかし、猫自身はサインを出していることがある。その一 […]
てんかん診療の進め方。厳密な診断基準に沿いながら、飼い主の感情を組み入れる。現場で役立つカスタマイズ。
1ヶ月間隔で2回、犬が発作を起こしたが、どう考えればよいかとの相談を受けた。てんかんの可能性はあると答えた。他の原因もあるかもしれないが、てんかんではないとは言えない。他の原因も頭の片隅に置きつつ経過を見守るのだ。基準か […]
目の色を変えて吠え続ける犬。この興奮をどう鎮めるか。素質や特性をつかんで適切な薬物療法を施す。
犬が吠え続ける、興奮し続けるといったように、ある行動が許容範囲内でおさまらずに、異常なまでに持続してしまう場合、脳内の一部の神経回路の異常が原因であることが報告されている。動物が何かの行動を起こすときには、神経の細胞に電 […]
脳炎? 特発性てんかん? 痛み? 典型的でない症状が見られたときは、決め打ちせず慎重に見極める。
興奮した後に声を上げて倒れるという症状は、2つの問題が考えられる。痛みかてんかんかだ。震えて口を大きく開けて叫び声を上げる。体は硬直し、排泄もしてしまう。飼い主にとっては恐ろしい光景だ。震えや硬直はけいれんを思わせる。一 […]
犬の尾追い行動は、行動学的問題と神経疾患の両方を並行して考えなければならない。抗うつ薬だけでなく、鎮痛薬も有効なことがある。
安定させるまではひと苦労なのに、その安定した状態はちょっとしたことで一瞬にして崩れ去ってしまう。神経に作用する薬剤には、すぐにはやめられないものがある。それは、突然やめると急激に悪化するからだ。抗てんかん薬や抗うつ薬の中 […]
頭を持ち上げない。目がうつろ。首が硬く感じる。こんなときは頚部痛を疑う。診療の進め方を徹底解説!
床置きの食器にドライフードが入っている。犬は当然首を下げて食べる。犬の一般的な食事風景だ。そのうち犬は食べるのをやめる。背骨と平行になるくらいの高さで首の位置を保って、動きが止まっている。犬はゆっくりと首を動かして横を見 […]
認知症の犬が感じる不安感。それを見て飼い主が感じる不安感。悪循環を断ち切るために、犬の薬物療法とともに飼い主の心のケアも欠かせない。
夜中にずっと息切れをしていたという犬。呼吸器系の症状は深刻な事態を連想させる。しばらく前からなんだか様子はおかしかった。ストレスに弱くなっているような気がしていた。聴診で肺や心臓に異常音はないし、レントゲンでも胸の中に問 […]