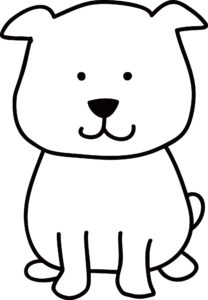子猫のけいれん‐3‐
発作がまったく見られなくなれば、念のため手元に置いてもらった併用薬を使うこともない。メインの抗けいれん薬だけで安定すれば、ひとまずは落ち着いた生活を送ることができる。ただし、これで解決ではない。やっとスタートラインに立ったに過ぎない。
猫のてんかんの診断は、国際標準の犬のてんかん診断の手順にしたがって、まずは進めるとされているが、まったくその通りにいかないことも多い。犬で基準を満たした場合に暫定的に診断することのできる、「特発性てんかん」とも限らないケースは多い。ちなみに、「特発性てんかん」とは、遺伝性、あるいは、おそらくは遺伝的な背景をもつてんかんのことを言う。
そもそも、猫で「特発性てんかん」が発生する割合は、犬と比較して低い。若くても、何かしら脳に起きた病気が元になって、発作が見られることの方が多いとされている。これは、「構造的てんかん」と呼ぶ。この猫の場合、抗てんかん薬で発作は抑えられているものの、元の原因が有るのか無いのかにまでは、まだ迫れていない。発作が抑えられていることと、脳の病気が特定されていることは、別の話なのだ。
脳のMRI検査や脳脊髄液検査が、次に選択される検査だ。抗てんかん薬を続けてもらいつつ、今後、発作が起きた場合の頻度や重篤度、さらに、普段の猫の行動や性格の変化、歩き方や姿勢の異常が現れないかを飼い主には十分に観察してもらう。少しでもいつもと異なる様子が見られれば、原因究明に向かうかどうかを相談しなければならない。