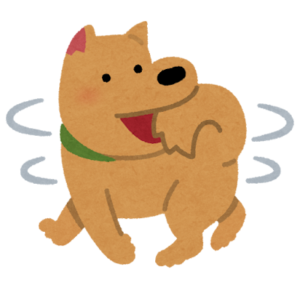頭を持ち上げない。目がうつろ。首が硬く感じる。こんなときは頚部痛を疑う。診療の進め方を徹底解説!
床置きの食器にドライフードが入っている。犬は当然首を下げて食べる。犬の一般的な食事風景だ。そのうち犬は食べるのをやめる。背骨と平行になるくらいの高さで首の位置を保って、動きが止まっている。犬はゆっくりと首を動かして横を見る。表情はうつろだ。見ようによってはてんかんを思わせる。
突然動作が止まって、意識がはっきりとしない。これは意識障害のように見えるかもしれない。てんかんとしてよく見られる症状ではないが、意識の減損を伴う焦点性発作ならありえる。触ってみると、首の筋肉が硬く感じる。てんかんの可能性は否定しないが、こうなってくると並行して検討するべき病態がある。頚部痛だ。
まずは、レントゲン。レントゲンでわかる頚部痛の原因は少ないが、最低限わかる疾患を除外する。明らかな異常所見がなければ、MRIや脳脊髄液検査に進むかどうかを飼い主に検討してもらう。検討中、あるいは、二次診療施設を予約してその受診日まで時間が空く間、つなぎとして消炎鎮痛剤や神経に作用する薬剤を処方する。この内服で症状が緩和された場合は、それで様子を見るのもひとつ。単に筋肉や靭帯の炎症、いわゆる寝違えや急に首を動かして痛めただけだったかもしれない。その場合は二次診療施設の予約はキャンセルでも構わない。
二次診療施設をキャンセルしないでさらなる検査に進んだ場合は、MRIでヘルニアや脊髄腫瘍がわかるかもしれないし、脳脊髄液検査で髄膜炎がわかるかもしれない。同時に脳の形の評価もできるし、てんかんの可能性について追加の情報を得ることもできる。状況に応じて脳波検査もすれば、絶対ではないがもっと核心に迫れるかもしれない。このような説明を飼い主にする。全体像を最初に示すのだ。診療とは診察と治療のこと。診察と治療の、この2点の間に道を引く。飼い主に納得と安心を感じてもらうためには、この診療のロードマップを手渡してあげる必要がある。