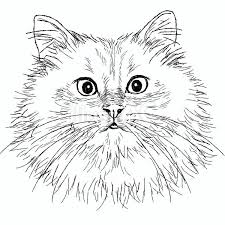1剤でコントロールができないてんかんは、2剤、3剤と微調整を重ねて安定させる。
てんかんの投薬治療にはスタンダードがある。初めから2剤や3剤を使うといったことをすると副作用が強く出る。突っ立たままボーっとする。触ればその刺激で目は開くが手を離すとユラ~っとして目を閉じてしまう。薬が効いている証拠ではあるが、さすがに生活に支障をきたす。
特発性てんかんと仮診断して処方をする場合は、まずは1剤を選択し、その後血中濃度を測定して薬用量を評価する。目標は3ヶ月に1回以下まで発作を減らすことだ。せめて1ヶ月に1回。しかし、それより多く発作が起きたときは増量する。こうして血中濃度を測定しながら基準値の上限に達するまで増やしていく。
同時に大学病院でMRI検査と脳脊髄液検査を受ける手続きをする。受診までの間にさらに発作が起きてしまい、最初の薬剤の血中濃度が上限まで達していたら、別の薬剤を追加する。このとき、増量しても効果が現れるまで時間がかかるので、そのつなぎとして別の薬剤を補助的に追加することもある。
このように、1剤から薬物治療を始めて調整をしていく中で、一時的に2剤や3剤を併用することもあるが、最初から複数を使うよりはボーっとするとか眠ってしまうといった副作用は出にくい。発作が目標の頻度以下になった段階で、補助的に追加していた薬を中止することを検討する。